インターネット上には無数の健康情報があふれていますが、そのすべてが正しいとは限りません。誤った情報に惑わされないためには、「一次情報」や「専門機関の発信するデータ」にアクセスすることが何より重要です。そこで本ページでは、厚生労働省や国立研究所、日本医師会など、信頼性の高い公的団体が提供する健康・医療情報のリンク集をまとめました。各サイトの特色や活用のポイントを詳しく紹介しており、日々の健康づくりから医療判断の参考まで幅広く役立ちます。「何を信じればいいかわからない」そんな時に立ち戻れる、信頼の情報源リストです。
信頼できる公的機関のリンク集
健康日本21アクション支援システム健康づくりサポートネット
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/
旧・厚生労働省「e-ヘルスネット」「e-健康づくりネット」「スマート・ライフ・プロジェクト」
主な内容・特徴:厚生労働省が運営する生活習慣病予防や健康増進のための一般向け情報サイトです。食事・運動・喫煙・飲酒など日常生活に関わる幅広い健康テーマについて、各分野の専門家による正しい知識をわかりやすく解説しています。
運営主体:厚生労働省(日本政府)
対象:国民一般(健康づくりに関心のある人)
活用ポイント:まず信頼できる公的情報源として参照すべき基本サイトです。例えば生活習慣病に関する基礎知識を事前にここで得ておくことで、インターネット上の怪しい健康法に惑わされにくくなります。専門家監修の情報に触れることで、医学的に根拠のある内容かどうかを判断する基盤となります。

厚労省 eJIM(統合医療情報発信サイト)
主な内容・特徴:厚生労働省による「統合医療」(補完・代替医療)情報の発信サイトです。ハーブやサプリ、民間療法など代替療法と科学的根拠の関係についてエビデンスに基づいた情報を提供しています。「情報の見極め方(一般の方へ)」というページでは、インターネット上の医療情報を吟味する具体的なポイントやクイズ形式の教材も掲載されています。
運営主体:厚生労働省(国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター受託事業)
対象:一般利用者および医療関係者
活用ポイント:代替医療や健康食品の効果をうたう情報を科学的視点で評価するのに役立ちます。例えば「〇〇を飲めば癌が治る」といったネット情報を見たとき、その療法に根拠があるかをeJIMで調べ直すことで、誤った民間療法に飛びつかないリテラシーを養えます。また「情報の見極め方」のコンテンツは医療情報全般のリテラシー教育教材としても有用です。

がん情報サービス(国立がん研究センター)
主な内容・特徴:日本で最も信頼性が高いがん専門情報ポータルです。国立がん研究センターが運営し、患者や家族を中心に一般、医療者、行政担当者まで広く利用されています。各種がんの解説、標準治療、臨床試験情報、統計データ、相談窓口など、「確かな」情報を網羅的に提供しており、月間数百万人が利用しています。
運営主体:国立研究開発法人 国立がん研究センター(がん対策情報センター)
対象:患者、その家族、一般、市民、医療従事者など幅広く対応
活用ポイント:がんに関する情報収集ではまずここを確認するのが鉄則です。例えばインターネット上で話題の民間療法や最新治療法があっても、がん情報サービスでエビデンス状況を確認することで、根拠のない療法に惑わされるリスクを下げられます。信頼できるデータに基づき正しい治療選択や意思決定ができるため、医療情報リテラシーの実践に直結するサイトと言えます。
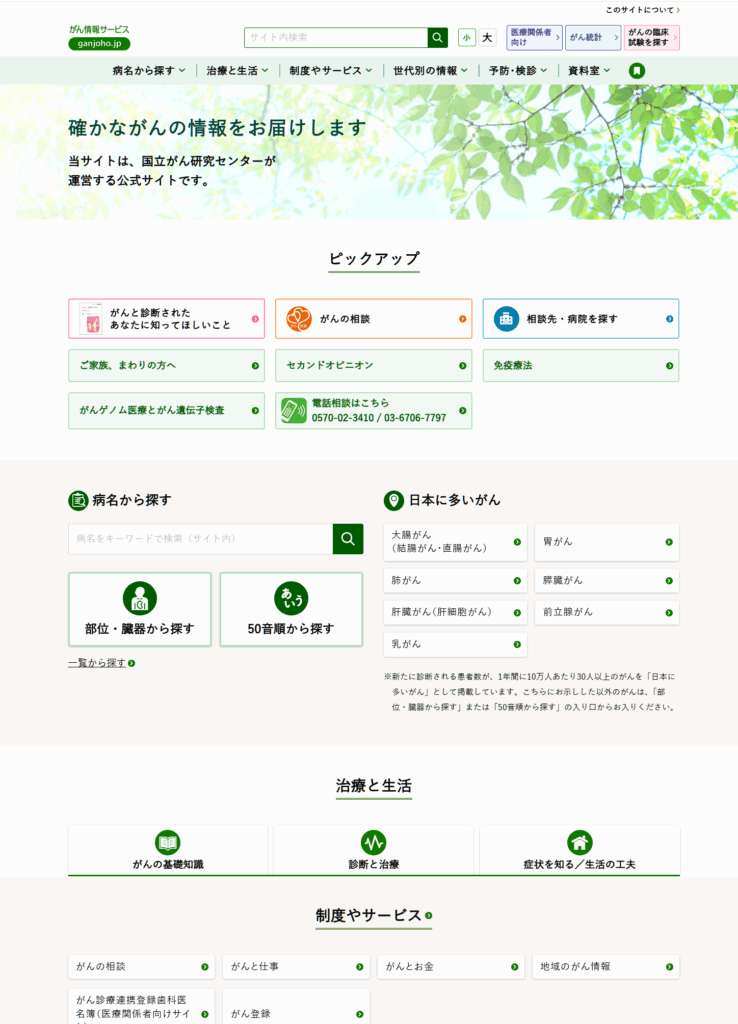
子どもの病気(国立成育医療研究センター)
https://www.ncchd.go.jp/hospital/sickness/
主な内容・特徴:日本の小児医療の中核である国立成育医療研究センターが提供する、子どもの病気に関する情報ページです。50音順の病名索引から、小児疾患の解説・症状・治療法・ケア方法などを専門医がわかりやすく説明しています。難しい病名から日常よく遭遇する症状まで網羅され、保護者がお子さんの病気を理解するのに役立つ内容です。
運営主体:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター
対象:小児患者とその家族(保護者)、一般
活用ポイント:子どもの体調不良時にインターネット検索に頼りすぎると、不確かな体験談や誤情報に振り回されがちです。本サイトで公的な小児医療の専門情報を調べれば、症状への正しい対処法や受診目安が得られます。育児世代の健康リテラシー向上に直結し、インターネット上の怪しい育児・医療情報をふるいにかける力を養えます。
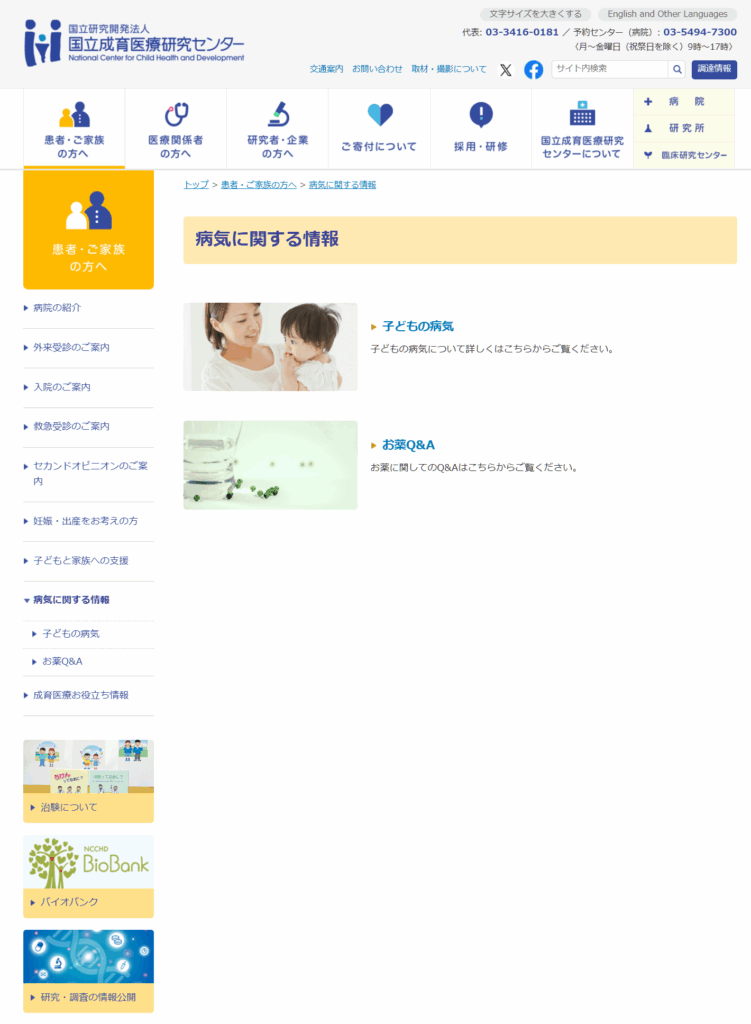
日本医師会「国民のみなさまへ」ページ
主な内容・特徴:日本医師会が一般の方向けに運営する公式サイトの情報ページです。医療・健康に関するニュース、正しい知識の普及を目的としたコラム、病気予防や検診啓発、医療制度の解説など、多彩なコンテンツがあります。医師会発行の「日医ニュース」から抜粋した健康情報(健康ぷらざ)や、子どもの健康相談(白クマ先生の子ども診療所)、サプリメントの注意点など専門家監修の記事が掲載されています。
運営主体:公益社団法人 日本医師会
対象:一般国民・患者
活用ポイント:医師による公式情報という点で信頼度が高く、健康に関する正確な知識の習得に適しています。例えばSNS上で話題の健康法があった場合でも、医師会の情報と照らし合わせてみることで、医学的に妥当か判断する材料になります。また、医療制度やかかりつけ医の仕組みに関する情報も提供されており、医療機関の賢い受診にも役立ちます。公的団体の視点から発信される情報に触れることで、玉石混交のネット情報を取捨選択する力が養われます。

日本インターネット医療協議会(JIMA)
主な内容・特徴:医療とインターネットに関する信頼性確保を目的に活動する民間団体です。医療分野のIT活用健全化と情報信頼性の向上を目指しており、インターネット上の医療情報発信サイトに対する認証(トラストマーク)制度やガイドライン策定を行っています。特に一般利用者向けに公開している「インターネット上の医療情報の利用の手引き」は、誰でも実践できる情報の見極めポイントを10項目にまとめたものです。例えば「情報提供者の主体が明確か」「営利目的が隠れていないか」「科学的な裏付けがあるか」など、具体的なチェック項目が提示されています。
運営主体:一般社団法人 日本インターネット医療協議会(有志の医師・企業等による団体)
対象:一般利用者、医療情報サイト運営者、医療関係者
活用ポイント:インターネット検索で得られる医療情報の信頼度を評価するための具体的な指針として活用できます。手引きに沿って情報源をチェックすることで、怪しい健康情報に騙されない目を養えます。例えば何かの治療法を調べた際、そのサイトの運営者や目的をまず確認し、JIMAの指摘する基準に照らして問題があれば、その情報を鵜呑みにしないといった判断が可能です。医療情報リテラシーを高める教材・基準として、一度目を通しておくことが強く推奨されます。
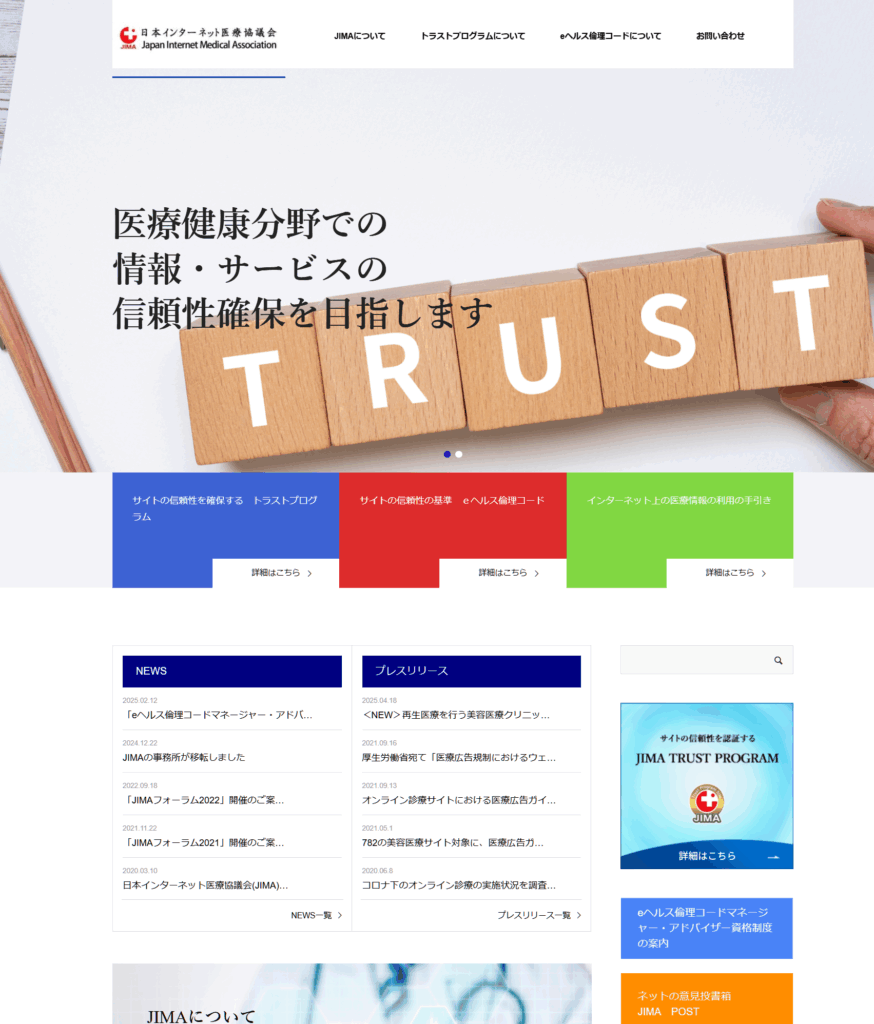
国立感染症研究所(感染症情報)
主な内容・特徴:国立感染症研究所(感染研)の公式サイトで、日本国内の感染症に関する信頼性の高い情報が集約されています。インフルエンザや新興感染症など各感染症の疫学情報、病原体の解説、予防法に関する資料、国内外の発生動向データ(IDWR週報等)や専門家によるQ&Aなどが提供されています。また、緊急時には最新の研究結果やリスク評価も公表されるなど、公衆衛生上重要な情報源です。
運営主体:国立研究開発法人 国立感染症研究所(厚生労働省管轄)
対象:医療関係者、研究者が主だが一般向けの情報も含む
活用ポイント:感染症流行時に不確かなデマ情報が飛び交う中で、確かな統計データや専門見解を得るのに不可欠なサイトです。例えば新型インフルエンザの流行時にネット上で様々な予防策が語られていても、感染研のサイトで正式なガイドラインやエビデンスを確認することで、正しい対策を取ることができます。難解な部分もありますが、厚労省や自治体の発表の根拠データにもなっているため、ニュースやSNS情報の裏付けを取るのに役立ちます。専門家レベルの情報に触れることで、一般の人でもデータに基づき冷静にリスク判断するリテラシーが養われます。
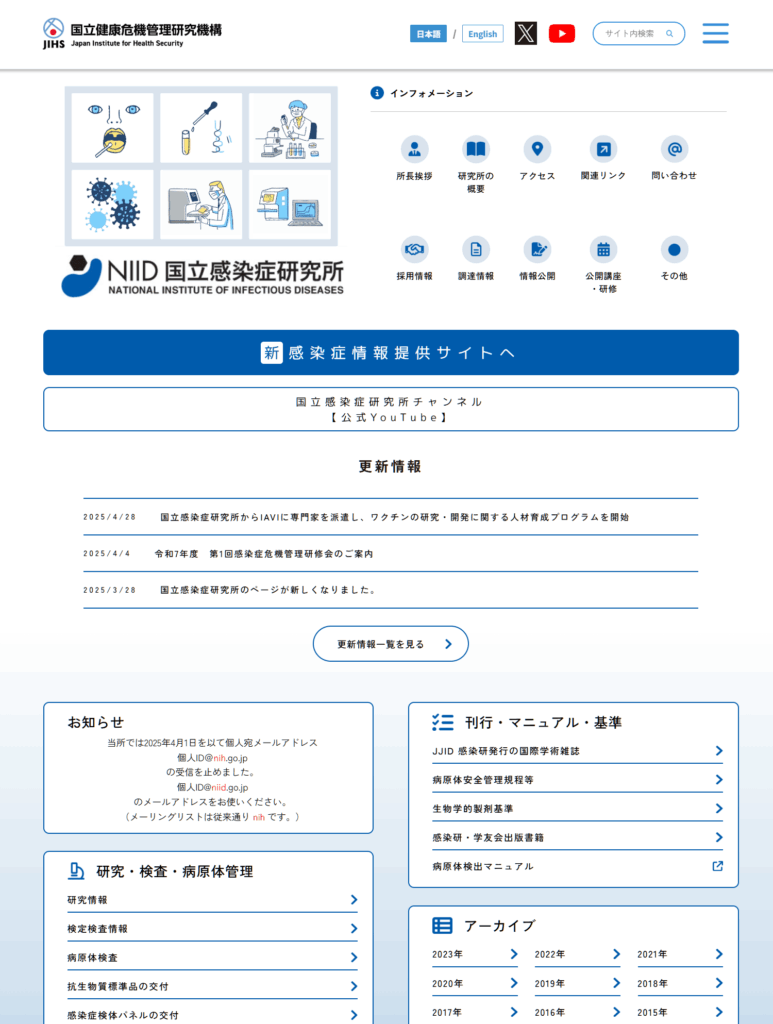
「健康食品」の安全性・有効性情報(HFNet)
主な内容・特徴:「健康食品」(いわゆるサプリメントや機能性食品)の効果や安全性について科学的根拠をまとめたデータベースです。国立健康・栄養研究所が運営しており、食品成分に関する正しい情報提供や健全な食生活の推進、健康食品による健康被害防止を主目的として運営されています。具体的には各素材(例えば○○というハーブ)の有効性に関する論文レビュー結果や、安全性に関する評価、他の薬剤との相互作用の有無などが閲覧できます。専門家向けの詳細データから、一般向けの基礎知識、関連コラム、Q&A、パンフレットまで情報は豊富です。
運営主体:国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所(国立健康・栄養研究所)
対象:研究者・専門家から一般消費者まで幅広く利用可能
活用ポイント:巷で宣伝されているサプリメントや健康食品の効果を、購入前にチェックするのに最適なサイトです。例えば「飲むだけで痩せる○○」といった広告を見た際、その成分名でHFNetを検索すれば、実際に減量効果があるのか科学的エビデンスを確認できます。もし「有効性が十分証明されていない」などの評価であれば、その商品広告は誇大かもしれないと判断できます。このように、健康食品の真偽を見極める力を身につける上で、公的機関のデータベースを活用することは極めて有効です。食品やサプリの安全性情報も載っているため、リスクを理解した上で適切に利用する習慣形成にもつながります。
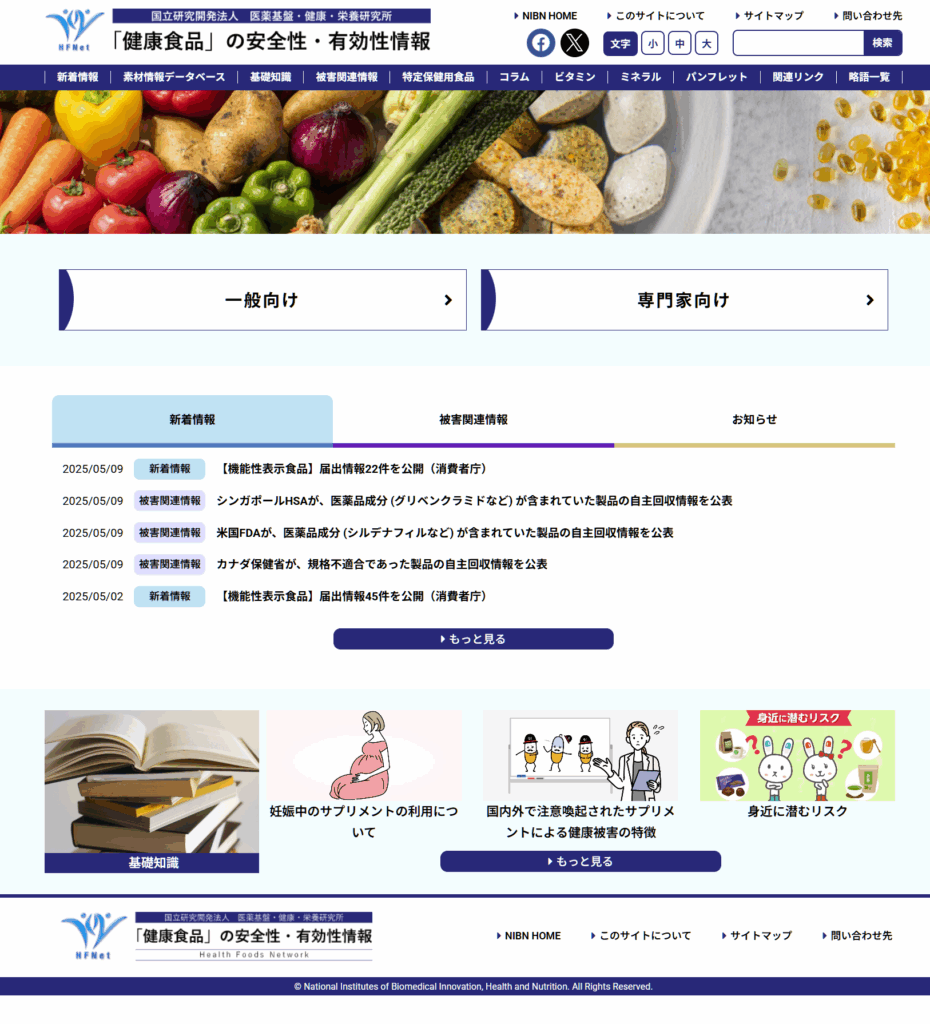
こころの情報サイト
旧「みんなのメンタルヘルス総合サイト」。令和5年4月より国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターに掲載。
主な内容・特徴:厚生労働省が運営するメンタルヘルスに関する総合情報サイトです。「こころの健康に関する情報を知ることからはじめよう」というコンセプトのもと、うつ病、不安障害、発達障害、認知症など心の不調や病気についての基礎知識を提供しています。症状や治療法の解説だけでなく、困ったときに利用できる相談窓口の案内、経済的・社会的支援制度の紹介、家族や周囲の人向けのサポート情報なども充実しています。難しい専門用語をできるだけ避け、イラストや図表も交えて解説しているため、精神医療の専門知識がない人でも理解しやすい内容となっています。
運営主体:厚生労働省(監修:国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 等)
対象:一般(こころの不調に悩む本人、その家族や支援者、幅広い国民)
活用ポイント:メンタルヘルスの分野はインターネット上に玉石混交の情報が多い領域です。自己流の誤った対処法や、根拠の薄い精神論などに影響されてしまうリスクを減らすため、公的機関が発信する正確な情報に触れることが大切です。本サイトを活用すれば、症状に対する正しい理解と適切な受診・相談先を知ることができます。例えばSNS上で「〇〇療法でうつ病が即治った」などの体験談を見ても、まずこのサイトでうつ病の標準的な治療法や回復までのプロセスを確認することで、極端な情報に振り回されず冷静な判断ができるでしょう。また、必要に応じて信頼できる相談機関につながることもできるため、インターネット上の情報だけに依存しない行動を取る手助けにもなります。公的なメンタルヘルス情報に常にアクセスできるようにしておくことで、こころの健康に関する情報リテラシーを着実に高めることができます。

以上、厚生労働省や国立の医療研究センター、日本医師会などが提供する信頼性の高い情報源をご紹介しました。これらのサイトをブックマークして活用することで、日々あふれる健康・医療情報の中から根拠に基づいた正確な知識を選び取る力が養われます。公的機関の情報を土台にしつつ、必要に応じて医療専門家へ相談することが、「医療情報リテラシー」を高め、納得のいく健康づくり・医療選択につながるでしょう。



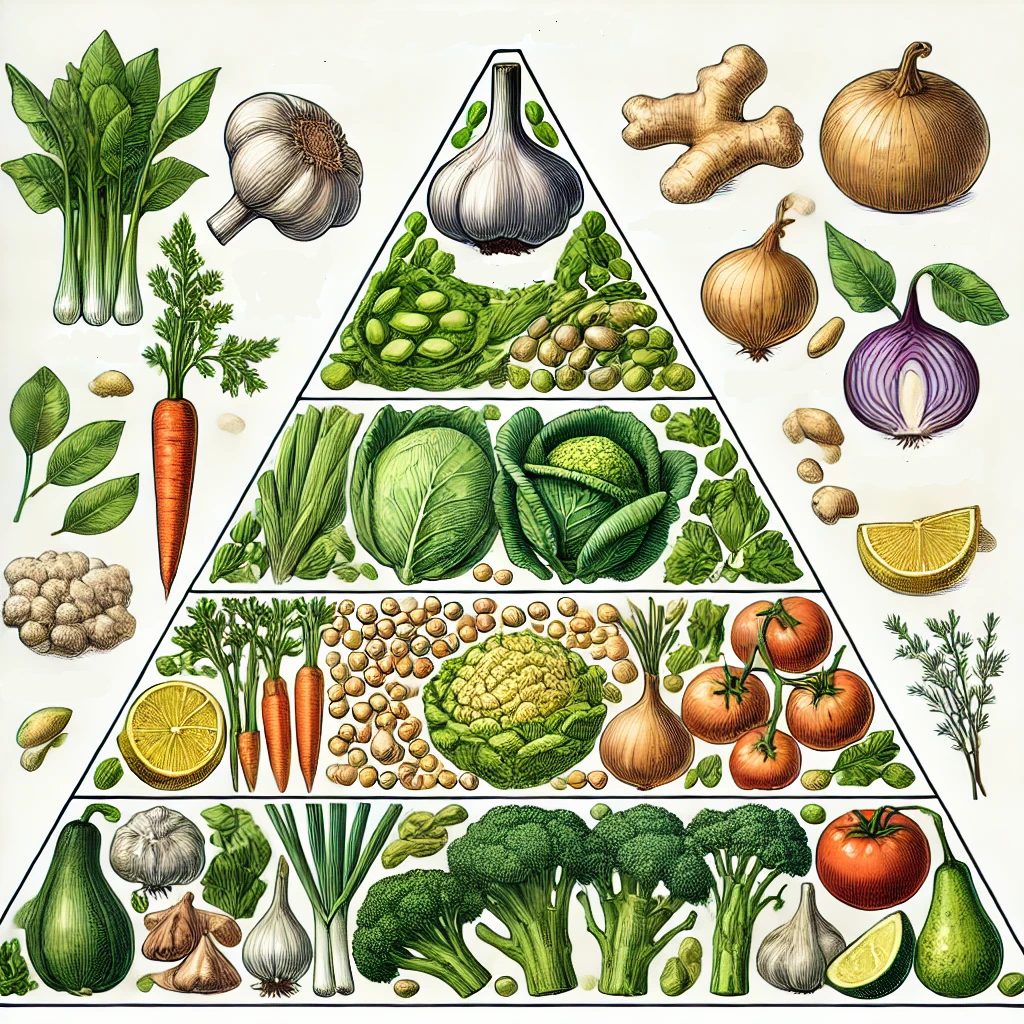










コメント